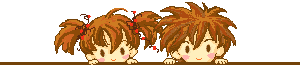 正解
正解久留倍官衙遺跡 (国指定史跡)
平成11年(1999)北勢バイパス建設前の発掘調査が開始され平成14年に飛鳥・奈良時代の正殿・脇殿から成る政庁と呼ばれる施設や、 租税として徴収した稲などを納めた倉庫群である正倉院が発掘された。 特に政庁の入り口である門は、格式のある八脚門で、全国的にも珍しく 伊勢湾の方角である東を向いている。 古代朝明郡の役所跡と考えられる。 この発掘の結果、平成18年(2006)7月に四日市では初めての国指定史跡に指定された。 朝明郡は、天武元年(672)の壬申の乱の際には大海人皇子(後の天武天皇)が、天平12年(740)には聖武天皇が訪れたとされている。
●補足説明 この久留倍の丘は、今の観音山観音寺(有縁寺)があった場所で明治22年(1890)に小学校の西に移転された。 また、室町時代の寛正元年(1460)に浄土真宗高田派の真慧上人がこの地で布教の為お堂を建て光明寺を創立するが、あまり広がらず、最終的に津市一身田に移り、専修寺を創建、真宗高田派の総本山となった。 現在、国宝建築物に指定されている。 明治時代までは大矢知地区の信仰の中心地で賑やかなところだった。 この地は見晴らしがよく、大軍を配置しやすく室町時代、南北朝時代には、久留倍山の合戦、垂坂山の合戦などが起こり、 また垂坂山・久留倍は大正天皇の皇太子時代に陸軍の演習が行われた。
問題5問すべて正解しました。
大矢知検定合格とし、認定書を発行いたします。
認定書発行
TOPに戻る