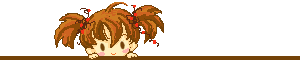 正解 正解観音山(庄屋山) 明治22年に久留倍から移設された、観音寺を中心にお堂・石仏が点在し昭和の中頃までは、小型遊具や猿の檻があり憩いの場として親しまれていた。 1 縁華山 有縁寺(真言宗・観音山観音寺) 大矢知町 創立・開基は不明。明治22年頃までは東谷の久留倍郷にあり、その地区の小字名に大門・ハセ町という地名が残っており大矢知村民の信仰の中心地だった。江戸時代に庄屋山であった所に移転し今日の観音山となった。 御本尊の十一面観音は頭の周囲に仏像が11面ある。全ての方角を見て、観音の慈悲で人々を救い、病を除き、罪を滅すると信じられている。 2 妙見堂 ひとつのお堂の中に仏様と神様が一緒に祀られる。 お堂の左側に妙見菩薩・右側に天満宮(天神様)が安置されている。 古文書によれば、武蔵国・忍藩から大矢知陣屋に赴任してきた役人が学問の神様・天満宮と武術の神様・妙見菩薩を祀ることが記されている。以前は妙見山にあり、更にその北側の大日山へ移転、その後、現在の観音山に移築した。 3 大日堂 大日如来尊(石仏)の由来については不明だが、堂前にある石柱には 大正9年5月27日と記載されている。この石仏はもともと大日山に祀られていたが、その後、三岐大矢知駅東の羽津用水の辺りに移され、更に戦後、現在の観音山に移設された。大矢知駅前に大日橋という小さな橋が残っている。 また、妙見山・大日山はともに、現在の大矢知幼稚園の北側付近にあったが、昭和6年(1931)に開通した三岐鉄道建設工事のために消滅した。 第5問に進む |